
SNSで商品のプロモーションを行う際は、「薬機法」の知識が必要不可欠です。薬機法は、化粧品や医薬品、医薬部外品をはじめ、場合によっては食品や雑貨まで、幅広い範囲に適用されます。
この記事では、薬機法に関する広告情報から、SNS運用に特化した注意点をまとめました。
薬機法の基本から具体的なNG表現、SNS特有の落とし穴までを理解し、違反や炎上に発展することのない、安全かつ効果的なSNS運用につなげましょう。
薬機法とは?
薬機法は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の通称。対象とする物の品質や有効性、安全性の確保、およびそれらを使用したときの保健衛生上の危害の発生や拡大の防止などを目的として定められています。
薬機法が規制しているのは、物の「販売」と「広告」についてです。この記事では、SNSでのプロモーションに深く関係する「広告」に焦点を当て、解説します。
次の製品カテゴリーに当てはまる場合は、SNSでのプロモーションも含めて、広告を作成する際に薬機法に留意してください。
- 医薬品
- 医薬部外品
- 化粧品
- 医療機器
- 再生医療等製品
- 体外診断用医薬品
食品や雑貨(健康食品や健康雑貨など)は、基本的には薬機法の対象外ですが、広告で医薬品や医療機器だと誤認させるような訴求を行うことは薬機法でNGとされています。効果や効能を謳う際には、表現方法に留意する必要があります。
医薬部外品とは
医薬部外品は、たとえば殺虫剤や生理用品、薬用入浴剤、薬用シャンプーなどが当てはまります。いずれも製品に「医薬部外品」という記載があります。
化粧品とは
薬機法で化粧品とされているのは、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物」(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律/第2条第3項より抜粋)です。
ファンデーションなどのメイク用品のほか、石けんや歯磨き類、香水、シャンプー、美容液などがこれに当たります。

「広告」と判断される3つのポイント
そもそも薬機法では、「広告」に該当するものの要件が次のように定められています。
- 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を向上させる)意図が明確であること。
- 特定医薬品などの商品名が明らかにされていること。
- 一般人が認知できる状態であること。
この3つの要件をすべて満たすと広告だと見なされるため、薬機法への留意が必要です。
BtoB向けの商材であっても同様に、上記の3要件を満たせば広告に該当し、規制の対象となります。
化粧品・健康食品の表現NG集
薬機法でNGとされている広告表現について、薬機法の対象カテゴリーの中から、SNS上やインフルエンサーによるプロモーションと親和性の高い化粧品と健康食品をピックアップし、まとめました。
化粧品
前提として、化粧品の広告表現は、化粧品の効能効果やメーキャップ効果として認められている56項目の範囲内で、事実に基づいて訴求することが認められています。
具体的には、シャンプーであれば「頭皮、毛髪をすこやかに保つ」「裂毛、切毛、枝毛を防ぐ」など、化粧水や乳液であれば「肌のキメを整える」「皮膚にうるおいを与える」などの項目が示されています。
化粧品の広告表現として注意すべきNG例は、次のようなものです。以下は全て使用できません。
- 目尻や口元の小じわがなくなります
- 10年前のお肌に!
- シワ、たるみの改善
- シミ、そばかすの除去
- 抗酸化作用でお肌の老化をシャットアウト
- エイジレス
- 若々しくリモデリング
- 重力に対抗する
- 肌の活性化
- 肌細胞の再生力を高める
なお、「エイジングケア」という表現には注意が必要です。「年齢相応のケア」とするなら可能ですが、「老化に対するケア」となると不可となります。
このように、ニュアンスの変化で使用可能か変わってくるため、以下に表現方法を詳しく説明します。
-
「アンチエイジング」の表現
SNSでは、アンチエイジングに関連する化粧品の投稿がよく見られます。
3要件を満たす広告においてこの効果効能を表現する場合、老化に対するケアを謳った表現はNG。たとえば、「目じりや口元の小じわがなくなる」「10年前のお肌に」など、若返りや老化を止めるといったことを想起させるような表現がNGに該当します。
一方、OKとされているのは、「年齢に応じたケア」や「エイジングケア」などの表現。OKとNGの表現の違いをしっかりと理解した上で広告表現を考えましょう。
-
誇大表現、虚偽の表現
「シワ、たるみの改善」や「シミ、そばかすの除去」など、効能効果の誇大表現や虚偽の表現はNG。
また、効能効果について、「保湿効果に満足しています」といったように体験者の声として言及することもNGです。
-
「浸透」の表現
肌への浸透を表現する場合は、表皮の角質層よりも奥への浸透を謳うことが禁止されています。肌への浸透を表現する場合は、必ず角質層までであることを分かるように記載する必要があります。
健康食品
医薬品や医薬部外品に該当しない健康食品は、医薬品と誤認させるような表現をすることが禁止されています。
たとえば、病気の治療や予防を目的とする効能効果、身体の組織機能の一般的増強や増進を目的とする効能効果、医薬品的な効能効果の暗示を語っているような表現は医薬品とみなされるため、NGです。
「がん予防」「高血圧改善」「肝機能向上」「免疫強化」などが具体的なNG例として挙げられます。
また、SNSでよく見かける「ダイエット」表現についても、注意が必要です。
「ダイエット」という言葉そのものが不適切というわけではありませんが、たとえば「脂肪燃焼」や「食欲抑制」など、薬理作用による痩身効果を謳うと医薬品とみなされるため、NGとなります
インフルエンサー投稿も注意!「個人の感想」もNG!
インフルエンサーがユーザーの一意見として体験談の投稿を行う場合でも、それがPR投稿であれば薬機法に留意しなければなりません。たとえ「個人の感想です」と記載しても、効能効果や安全性について言及する内容のものは認められません。
インフルエンサーが企業の依頼を受けて薬機法に違反する投稿を行った場合は、依頼元の企業だけでなく、インフルエンサー自身も責任を問われる可能性がありますので、十分に注意しましょう。
ちなみに、インフルエンサーが企業の依頼を受けて商品に関する投稿を行う場合は、景品表示法(景表法)に違反する「ステルスマーケティング」にならないよう、PR投稿であることを明記するといった注意も必要です。SNSのプラットフォームごとのPR投稿時のポイントを以下にまとめましたので、あわせて確認しておきましょう。
関連記事:ステルスマーケティング(ステマ)規制とは?インフルエンサー案件は要注意!
SNS媒体ごとのステマ対策機能
媒体ごとに、PR表記やブランドコンテンツであることを示し、広告主との関係性を透明化する機能があります。薬機法に関連してインフルエンサーに投稿を依頼する場合、こうした機能も活用するようにしましょう。
X(Twitter)
これまでは投稿テキストに、PR投稿だと分かるハッシュタグを含める手法がよく利用されていました。多いのは、 「#広告」「#有料パートナーシップ」「#スポンサー」「#PR」などのハッシュタグです。
しかし、Xでは、6月からハッシュタグを含む投稿の広告配信ができなくなっています。そのため、PR投稿で広告配信を行いたいという場合はハッシュタグを使わず、本文中にプレーンテキストで「PR」や「提供:◯◯社」といった表記を入れるようにしてください。
関連記事:【X(Twitter)NEWS】ハッシュタグ付き広告が廃止|2025年6月27日から
Instagramの場合は、Instagramが提供するブランドコンテンツツールの利用が推奨されています。インフルエンサーは、ブランドコンテンツツールの「タイアップ投稿ラベル」を活用しましょう。ブランドコンテンツの設定を行った投稿は、そのまま広告としても配信できます。
なお、アルゴリズム上の制約は現状みられませんが、「#PR」 や 「#タイアップ」 といったPRハッシュタグ表記は非推奨とされています。
関連記事:Instagramのタイアップ投稿ってなに?ブランドコンテンツツールの使い方や分析方法
TikTok
TikTokにもブランドコンテンツの機能があります。ブランドコンテンツ機能を用いて「プロモーション」というラベルを動画に付けましょう。
YouTube
動画に「プロモーションを含みます」というラベルを付けましょう。すると、動画の再生を初めて最初の10秒間に、動画の左上に「プロモーションを含みます」というテロップが表示されます。
参考:YouTube「有料プロダクト プレースメント、スポンサーシップ、おすすめ情報を追加する」
参考:YouTube「お子様やご家族向け: 有料プロモーションとは」
見落としがちな薬機法の注意点・チェックリスト
薬機法に関して、よくある勘違いや見落としをピックアップしました。こちらもチェックして、薬機法について正しい知識を身につけましょう。
ビフォーアフター画像
これまでの項で、化粧品において薬機法で認められていない効果効能を謳う広告はNGだと述べてきました。その一環として、たとえば「乾燥による小ジワを目立たなくする」などの効能を有する化粧品で、ビフォーアフター画像を使用した訴求をすることも、認められていない効能効果を想起させるためNGとされています。
しかし、同じビフォーアフター画像でも、洗浄効果や保湿効果を示す画像など、あくまでも薬機法で化粧品の効能として認められている範囲であれば、ビフォーアフター画像を使用することは可能です。
メールマガジン
広告という意識でメールマガジンを作成していない場合であっても、その内容が広告の3要件を満たせば広告に該当するため、薬機法の対象となります。自社のメルマガが広告に該当するかどうかを確認し、該当する場合は薬機法に違反する内容になっていないかをチェックしましょう。
ちなみに、メールマガジンを配信する際は、広告宣伝メールについての規定を定めた「特定電子メール法」にも留意する必要があります。同法には、たとえば送信者の住所や連絡先、配信停止の手続きができるURLやメールアドレスなどの記載が義務づけられています。
参考:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/m_mail_pamphlet.pdf
投稿前の最終チェックリスト
SNSに投稿する前に、投稿の内容が何らかの法律に抵触していないか、確認しておきましょう。
- 取り扱う商材のカテゴリー(医薬品、化粧品、健康食品など)を正しく理解しているか。
- その投稿に記載した表現は、そのカテゴリーや審査で認められた効能効果の範囲内か。
- 効能効果が誇大広告や虚偽に当たらないか。
- 体験談やビフォーアフター画像は、承認外の効能効果を想起させないか。
- 医薬品や医療機器と誤認させる表現ではないか。
少しでも疑問に思うことがあれば、確認するようにしておくと安心です。
そのほかの投稿前チェックリストもあわせて確認しておきましょう。炎上リスクやトラブル防止につながります。
参考記事:SNS投稿作成・確認承認のための注意点!投稿チェックリスト
まとめ:表現に気をつけてSNSを上手に使おう
薬機法について、化粧品や健康食品など特にSNS上での広告やプロモーションと親和性が高いカテゴリーを中心にまとめました。細かな表現で気になることがある場合は、広告主の企業や行政などにしっかりと確認することが大切です。
- 化粧品は、薬機法で効果効能として認められている項目の範囲内で表現すること
- 健康食品は、医薬品と捉えられるような表現を用いない
- 企業だけでなく、PR投稿を行うインフルエンサーにも薬機法の規制が適用
以上の3点を踏まえてプロモーションを行うようにしましょう。
SNS広告やインフルエンサーマーケティングに不安がある、運用について相談したい、SNSの成果を保ちながら話題化を進めたいといった場合は、ぜひコムニコへご相談ください。
化粧品カテゴリー(ヘアケア用品)で、SNSの運用を支援し、ブランド立ち上げから「SNSで9秒に1回の頻度で投稿*」されるほどの話題化を実現した実績もございます。
* 2024年2月7日~2月29日までのX(Twitter)とInstagramでの+tmrに関する口コミ投稿数(ファイントゥデイ調べ)
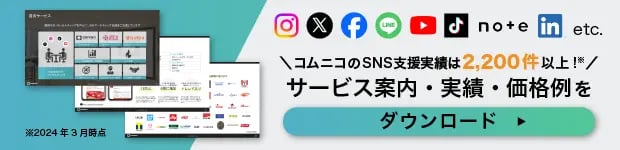 >>コムニコとは?SNS運用支援サービス資料・実績をダウンロード
>>コムニコとは?SNS運用支援サービス資料・実績をダウンロード
>>SNS運用支援・プロモーションキャンペーンについてコムニコに相談する
SNS運用のプロフェッショナルであるコムニコが、貴社のブランドや商品、サービスに合わせたSNSマーケティングを支援いたします。ぜひお気軽にご相談ください。
-1.jpg?width=90&height=90&name=S__14540804%20(1)-1.jpg)
フリーランス編集者として大手出版社の雑誌・書籍を担当後、コムニコへ。SNSコンテンツクリエイターとして、高知県観光のSNS支援では9ヶ月でフォロワーを約15倍に拡大など、さまざまな業種のアカウント支援を担当。「We Love Social」では、編集長として100以上の記事を執筆し、メディアを月間最大37万PVに成長させた。本質的な信頼を育む「ラバブルマーケティング」を実践する、SNSエキスパート協会認定講師(SNSエキスパート検定上級資格保有)。











