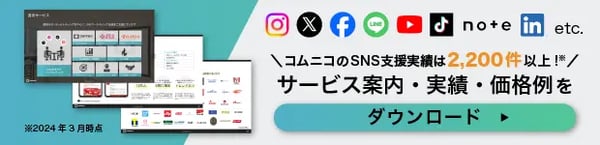TikTokを「若者のアプリ」だと思っていませんか?
今やそのユーザーは全年齢層に広がり、購買力のある大人も多く利用するプラットフォームへと進化しています。
この記事では、TikTok Shopについて解説し、そこから直結するECマーケットの規模や経済効果をデータから解説。変わりゆくSNSやECの未来、そして今TikTok Shopに参入すべき理由をご紹介します。
なぜ今EC連携?可能性を秘めた「TikTok Shop」とは

「TikTok Shop」は、TikTokのEC機能のこと。日本国内においては2025年6月末にリリースされました。一連の購買プロセスをTikTokアプリ上で完結できるのが特徴です。
TikTok Shopは通常のフィードを流れるショート動画やライブ配信、ショーケースタブと連携しており、いずれのコンテンツからも直接商品が購入できます。これによって、ユーザーが商品を知って興味を持つところから、購入に至るまでの一連の購買プロセスをTikTokのアプリ上で完結できるようになっています。
たとえば、フィードを流れる動画であれば、動画内の商品タグのタップで商品詳細ページに移動し、そのまま購入が可能です。また、ライブ配信であれば、動画内にピン留めされた商品のタップ、またはショッピングカートのアイコンのタップで、直接購入ができるようになっています。

TikTok Shopの仕組みや機能、使い方については以下の記事でも解説しています。
参考記事:TikTok Shopとは?スタートダッシュを決める始め方・使い方・導入手順を解説!
TikTokの市場規模―推定消費額は2,375億円

ここで、TikTokについての概要をおさらいしておきましょう。
縦型短尺動画プラットフォーム「TikTok」は、若者が単にダンスなどの短い動画を見て楽しむだけに留まらず40代以上の利用者も増加しています。さらに、動画やライブで見た商品を購入したり観光地に赴いたりと、消費行動を促すプラットフォームとして巨大な経済圏を築きつつあります。
TikTokが2025年3月にマクロミルグループを通して調査を行ったところ、TikTokユーザーの33.9%が、TikTokのコンテンツを見て商品やサービスを購入した経験があることが分かりました。

2024年のTikTok経由の推定消費額(TikTokで商品やサービスの広告、紹介コンテンツを見たことによる消費額の推計)は、2,375億円。2023年の1,772億円から約603億円増加し、割合としては37%の成長と、TikTokによる消費が前年よりもさらに拡大していることがうかがえます。

さらに、TikTokをきっかけとして生まれた消費活動をもとに試算した国内名目GDPへの貢献額は4,855億円。これには、TikTokで見た商品の購入や、TikTokで紹介された飲食店や観光地での消費だけでなく、企業がTikTokに広告を出したり、TikTokに投稿する動画を制作したりすることで発生した経済活動、TikTokで得た情報をきっかけに消費者が行動を起こし、それが他の産業にも波及して生み出された経済効果なども含まれます。
つまりTikTokは、直接的な購買を促すだけでなく、広告やコンテンツ制作、さらには他の産業への広がりを通じて、日本経済に大きな影響を与えていると言えます。

加えて、国内で創出された雇用者数は4.2万人と推計されています。TikTokを運用する企業のマーケティング担当者に対して行った調査では、51.9%が「TikTokが採用活動に影響を与えている」と回答し、TikTokによる人材の獲得に新たな可能性を感じていることがうかがえました。

参考:https://newsroom.tiktok.com/tiktok-socio-economic-impact-report-june-2025?lang=ja-JP
TikTok Shopに参入すべき3つのメリット
SNSを通じて商品を販売したいと考えているのであれば、TikTok Shopは今まさに参入すべきプラットフォームです。
その理由は、大きく3つあります。
メリット①:「これから拡大」先行者利益が得られる
商品の販売やライブコマースにInstagramを活用している企業は多くありますが、TikTok Shopを利用している企業はまだ少ないのが現状です。今参入することで先行者利益が得られる可能性は高いでしょう。
消費者リサーチ会社のノウンズによると、2025年7月時点でTikTok Shopのサービスを知っていると答えた人は全体の18%。認知している人もまだ少ない状況ですが、そのうちの約半数である52%がTikTok Shopを「使ってみたい」と回答しており、将来的なユーザーの増加に大きな期待が持てます。また、これから認知が広がっていくことを考えれば、それに比例して「使ってみたい」という人が増えるというポテンシャルも感じられます。
 爆発的なユーザー増加や競合参入の前にTikTok Shopを始めておけば、TikTok Shop内での市場シェアを多く獲得できる可能性があります。また、TikTokユーザーとより多くの接点を持てるようになり、他社のブランドよりも身近に感じてもらうことができるようになるでしょう。
爆発的なユーザー増加や競合参入の前にTikTok Shopを始めておけば、TikTok Shop内での市場シェアを多く獲得できる可能性があります。また、TikTokユーザーとより多くの接点を持てるようになり、他社のブランドよりも身近に感じてもらうことができるようになるでしょう。
メリット②:「予定外の購買」消費行動の変化を捉える
TikTokのユーザーは、動画から最新の情報やトレンドをキャッチアップするだけでなく、そこから何らかの消費行動にもつなげています。2025年3月のマクロミルの調査では、「TikTokをきっかけに何らかの行動を起こした」と回答した人が、TikTokユーザーの58.6%にものぼりました。
 特に多かった行動は、「TikTokで紹介された観光地やお出かけスポットを訪れた(36.5%)」と「TikTokで紹介された飲
特に多かった行動は、「TikTokで紹介された観光地やお出かけスポットを訪れた(36.5%)」と「TikTokで紹介された飲
食店を訪れた(36.0%)」。また、30.0%のユーザーが「予定外の購買をした」と回答しました。

このようにTikTokユーザーにとっては、動画を見て行動を起こす、商品を購入するということが当たり前になっています。まだ動画を活用していないのであれば、とにかくまずは動画という接点を追加することをおすすめします。
実際の事例として、熊本県のトマト農家である「まいひめおじさん」は、どんなに質の高い商品をつくっても認知が広がらないことに課題を感じ、TikTokの動画を使って情報発信を始めました。栽培の様子や農業の実情をユーモアを交えて語ったところ、大きな反響を呼び、1本6,000円のトマトジュースが3日間で100本完売するという“TikTok売れ”に。メディア露出も増え、全国の飲食店や小売店からの問い合わせにもつながっています。
@maihimeojisan トマトジュースについて#熊本 #トマト #トマトジュース #農家 ♬ 感動シーンに合うピアノ曲、BGM - しゅうまっちゃ
また、着圧ソックスの「メディキュット」は、TikTok広告を活用して、日常で実際に使っているシーンがイメージできる動画を展開し、商品に親しみを持ってもらえるようにしたところ、大きな成果を獲得。検索数や売上が、前月比で50%以上増加しました。これによって、TikTok広告が商品の認知から購入までのすべてのフェーズに強い影響を与えることが実感できたといいます。

メリット③:「TikTok毎日視聴」可処分時間の変化を捉える
2025年3月のマクロミルの調査によると、TikTokユーザーのうち、ほぼ毎日TikTokを視聴していると回答した人は61.5%にのぼりました。こうしたユーザーにとってTikTokは生活の一部として馴染んでおり、毎日の移動時間やリラックスタイムをはじめとする可処分時間に視聴して楽しんでいることがうかがえます。

近年は、テレビ離れが進み、スマートフォンの利用時間が増えていると言われています。それにあわせて広告の出稿先を調整することで、より効果的な広告活用が可能になるでしょう。TikTokのフィード投稿だけでなく、TikTokの広告活用もぜひ視野に入れてみてください。
参考:https://www.hakuhodo.co.jp/news/newsrelease/117303/
デメリットは?TikTok Shopで失敗するのはこんな企業
せっかくTikTok Shopに参入しても、ただ動画を発信して商品を販売するというだけで成果が上がるわけではありません。成果が上がらなければ、コストや人手ばかりがかかってしまい、結果マイナスになってしまうこともあるでしょう。
特に企業が陥りやすいTikTok Shopでの失敗は、次のようなものです。
データ分析の失敗→分析をすればROAS1000%超えも!
感覚だけに頼ったり、データをただ眺めながら運用するだけでは、思うような成果は得られません。しっかりとデータ分析を行い、どのような動画が好まれるのか、どうすれば伝えたいことが伝わるのか、よりコンバージョンにつながる内容はどのようなものかといった示唆を次の施策に生かすことで、理想とする成果に近づけることが大切です。
セブン&アイ・ホールディングスの事例では、プライベートブランドで展開する冷凍ピザ「金のマルゲリータ」のリニューアルに合わせて、TikTok広告を活用しました。

その際、調査をしっかり行い、データを分析してどのような動画がより効果が高いのかを見極め、すぐに施策に反映。その結果、ROASが1,000%を超え、商品の売上にも好影響があったといいます。
参考:https://markezine.jp/article/detail/46738
この事例のように、TikTok Shopで成功を収めるには、データ分析を正しく行って戦略に生かすことが必要不可欠です。
トレンドに乗っただけ、の失敗→自分に近い「ナノインフルエンサー」活用も検討を
SNSでは、インフルエンサーを活用した広告施策がよく行われています。そうしたトレンドに乗って、とにかくフォロワーの多いインフルエンサーに商品を紹介してもらえば売れるのではと考えるのは、失敗のもとです。特に、案件感(広告っぽさ)が漂う投稿は、ユーザーに嫌われます。

(出典:TikTok ILLUMINATE2025/ノウンズセミナーより)
ノウンズの調査によると、インフルエンサー施策において、フォロワー数1万人未満のナノインフルエンサーが購買のきっかけになったという人が最も多いという結果が得られています。この結果が示すのは、単純にフォロワー数が多ければそれだけ売上につながりやすいというわけではないということです。

(出典:TikTok ILLUMINATE2025/ノウンズセミナーより)
重要なのはフォロワー数ではなく、「広告色が薄く、口コミがリアルだと感じられる」こと。インフルエンサーとして成功している人よりも、自分と近い目線だと感じている人の言葉で語られる内容の方が、リアルで説得力が感じられます。
また、ただ商品や商品説明をなぞって紹介しているような投稿よりも、その人なりの使い方とその人なりの言葉で紹介されているとわかる投稿の方が、買いたいと感じる人が多いというデータも見られています。まさにこれも、「広告色が薄く、口コミがリアルだと感じられる」投稿だと言えるでしょう。

(出典:TikTok ILLUMINATE2025/ノウンズセミナーより)
先の項でご紹介した着圧ソックスの「メディキュット」の成功事例も、テレビCMなどのように商品を綺麗に魅せる動画ではなく、リアルな日常の使用シーンをクリエイティブに取り入れて訴求したことが、成功要因といえるでしょう。
成功例を真似ただけ、の失敗→自社ブランドにアレンジ
世の中では、さまざまな企業の成功事例や、成功のセオリーが紹介されています。それを取り入れて打った施策であれば、一定の効果は得られるかもしれません。しかし、それには重大な落とし穴があります。
たとえば、再生回数が伸びやすい動画の構成を模倣して、同じような動画を制作したとします。すると、再生回数自体は伸びるかもしれませんが、イメージが元の動画と被ってしまい、元の動画と同じ企業だと勘違いされたり、その企業の印象に自社の印象が影響を受けたりと、ブランディングや商品の想起に悪影響が出ます。

(出典:TikTok ILLUMINATE2025/TikTokショートコンテンツセミナー)
このように、安易な模倣はむしろ失敗につながる可能性があります。成功例に学ぶとしても、なぜその施策がうまくいっているのかという核心を捉え、単なる真似ではなく、自社ブランドならTikTokユーザーにどう届けるべきかという視点で、その核心につながる施策を立てるようにすることが大切です。
まとめ|TikTok Shopを活用して売上アップを!マーケティングを加速させよう
TikTokの推定消費額は2,375億円、日本の名目GDPへの貢献額は4,855億円、雇用の創出数は4.2万人と、TikTokの日本経済への影響はますます大きくなっています。TikTok Shopがスタートしたことでその動きはより加速していくでしょう。TikTok Shopはまだまだ認知が低いサービスですが、高いポテンシャルを持ったサービスであり、企業のマーケティングにおいても、ぜひ活用したいものであることがお分かりいただけたのではないでしょうか。
そのポテンシャルを最大限に引き出すには、データの分析と、その結果に基づいた独自戦略の立案が不可欠です。
しかし、自社のEC戦略を進めながらTikTok Shopの戦略や効果最大化を考えるのは、なかなか簡単にできることではありません。TikTokの戦略立案や売上効果の最大化は、その道のプロに相談するのがおすすめです。
株式会社コムニコは、SNSの黎明期から企業のSNS運用支援を行ってきました。TikTokをはじめとするSNSは、頻繁に機能やルールのアップデートが行われたり、新たなトレンドが生まれたりと、日々変化しています。
そうした変化をいち早くキャッチアップし、企業やブランドに合わせて活用方法を提案できることが、SNS運用支援を専門に行う企業の強み。コムニコでは、TikTokの開設支援やTikTok広告の活用支援、動画制作など、さまざまな形でのご支援が可能です。まずはお気軽にご相談ください。
-1.jpg?width=90&height=90&name=S__14540804%20(1)-1.jpg)
フリーランス編集者として大手出版社の雑誌・書籍を担当後、コムニコへ。SNSコンテンツクリエイターとして、高知県観光のSNS支援では9ヶ月でフォロワーを約15倍に拡大など、さまざまな業種のアカウント支援を担当。「We Love Social」では、編集長として100以上の記事を執筆し、メディアを月間最大37万PVに成長させた。本質的な信頼を育む「ラバブルマーケティング」を実践する、SNSエキスパート協会認定講師(SNSエキスパート検定上級資格保有)。