AI学習される?X(Twitter)の利用規約をチェックしよう!

国内月間アクティブユーザー数が6,700万を超え、企業による活用も年々増えているX(Twitter)。すでに運用を始めて数年が経ったという企業アカウントもあると思いますが、そうした中でも定期的に見直したいのがサービス利用規約です。
利用規約は、定期的に改定されています。最近では、投稿がAIの学習データとして活用されることが新たに明記され、話題となりました。規約改定の内容は企業のアカウント運用に関係するものとそうでないものがありますが、重大な改定を見逃してうっかり規約違反をしていたということがないよう、ここで改めて確認しましょう。

X(Twitter)の利用規約とは?
X(Twitter)の利用規約とは、X(Twitter)を利用する際の条件やルールを規定したものです。
ユーザーはこれを遵守する必要があり、もしも規約に違反した場合、X(Twitter)はユーザーに対して、コンテンツの削除や公開範囲の制限、X(Twitter)へのアクセスの停止、法的措置などの強制措置を取ることができるとしています。
最近では、機械学習やAIに関する内容が明記されたことによって、大きく話題になりました。これを受けて、今後のX(Twitter)の運用の仕方について改めて考えるユーザーも、特にクリエイターを中心に多く見られました。
このように、利用規約の変更ひとつで、アカウントの運用方法を見直さなければならなくなる可能性もあります。利用規約や改定内容を確認することで、規約違反だけでなく、思わぬリスクを避けられるようにしましょう。
X(Twitter)の利用規約の主な変更点
X(Twitter)の利用規約において、2024年11月に大幅な規約改定が行われました。主に以下の点が新たに記載されています。
・AI学習へのコンテンツの使用
利用規約に、ユーザーが投稿したコンテンツをX社の機械学習や人工知能モデルのトレーニングに使用するということが明記されました。
実は、投稿が機械学習や人工知能モデルのトレーニングに使用されることは、すでに「データ処理についての詳細情報」に記載され、運用が始まっていました。しかし、2024年11月の改定で明確に利用規約に記載されたことにより、多くの人の目に触れて話題となりました。
自社の投稿テキストや画像、動画などを、機械学習や人工知能モデルのトレーニングに使用されたくないという場合は、アカウントの設定変更によりトレーニングへの使用を回避することができます。詳しい設定方法は、のちの「AI学習への使用を回避する方法」の項にて解説していますので、そちらを参考にしてください。
・スパムや中身のないアカウントへの対応
スパムや詐欺、なりすまし、偽装などの行為を行うアカウントに対するポリシーが「信頼性」の項にまとめられました。これによって、たとえば投稿やリプライ、DMで、大量の投稿や同じ内容の投稿、無関係な投稿などを一方的に送信することといった禁止行為が細かく規定されています。
X(Twitter)には、投稿コンテンツに対して広告収益を得られる「Creator Ads Revenue Sharing program」という制度があり、その収益の欲しさに、バズった投稿へ意味のないリプライを繰り返すアカウントが散見されます。こうしたアカウントは、ユーザー間で「インプレゾンビ」と呼ばれ、通常のユーザーに迷惑がられています。「信頼性」の項は、インプレゾンビの抑制を主な意図として設けられました。
X(Twitter)を利用できる人
利用規約の最初の項目には、「本サービスを利用できる人」として、X(Twitter)の利用資格を持つ人が記載されています。簡単にまとめると、X(Twitter)の利用には以下のような条件があります。
- X(Twitter)の利用規約やポリシーに同意すること
- 13歳以上であること
- 会社や組織などのアカウントを運用する場合は、規約に同意する権限を有していること。または会社や組織を規約に拘束する権限を有していること
企業アカウントの場合は、ブランドや商品のリリースに合わせた誕生日を設定したくなりますが、2011年よりも最近を設定してしまうと、13歳以下であると判定されて凍結などの制限を受ける場合があります。注意しましょう。
X(Twitter)上のコンテンツについて
利用規約では、X(Twitter)に投稿するコンテンツに関して、簡単にまとめると以下のように規定されています。
- 投稿するコンテンツは、他の人に共有して差し支えない内容のみ
- X(Twitter)から取得したコンテンツや素材の使用は、ユーザーの自己責任
- 全てのコンテンツについて、その作成者が単独で責任を負う(X社は責任を負わない)
- X社は、規約に違反するコンテンツを削除する権限を持つ
- コンテンツがコピーされ、著作権が侵害された場合は、指定の窓口に報告する
その上で、コンテンツの権利については、以下のように記載されています。
- 作成者は、自ら送信や投稿、表示をするあらゆるコンテンツに対して所有権を持つ(他のコンテンツに組み込まれたユーザーの音声、写真、動画も含む)
- X(Twitter)上で送信、投稿、表示されたコンテンツは、X社があらゆるメディアや配信方法で、ユーザーに報酬を支払うことなく使用するライセンスを持つ(このライセンスにはAI学習への使用も含む)
- ユーザーは、X(Twitter)上で送信、投稿、表示されるコンテンツに関して、規約に書かれた権利の許諾に必要なすべての権利やライセンスを有している。または、規約に書かれた権利を許諾できる法的権限がある。それ以外の場合、そのコンテンツは著作権などの権利の対象となる素材を含まない
X社の利用規約に沿って、放送・配信・リポスト・プロモーションに対して他の個人や企業が利用できるようにすることに同意するものと明記されています。
AI学習への使用を回避する方法
前述のように、利用規約にはユーザーの投稿がAIの学習に使用されることが明記されましたが、アカウント設定の変更により、それを回避することができます。
X(Twitter)上の投稿をAI学習に使われたくない場合-オプトアウトの方法
X(Twitter)に投稿した情報をAI学習に使われたくない場合は、作品やアカウントを削除するのではなく、設定からAIトレーニングへのオプトアウトをするようにしましょう。
設定方法は、もっと見る>設定とプライバシー>プライバシーと安全>データ共有とカスタマイズ>Grokを選択してチェックボックスを外すというものです。こちらの設定方法はヘルプページにも記載されています。

参考:https://help.x.com/ja/using-x/about-grok
アカウントの行為のルールと留意点
「プラットフォームの使用に関するガイドライン」には、「アカウントの行為のルールと留意点」がまとめられています。前述したように、インプレゾンビへの対策を主な目的とした規約の改定により、スパムなどの行為を行うアカウントに対するポリシーが強化されました。「アカウントの行為のルールと留意点」では、具体的にどのような行為がスパムと見なされるのかが挙げられていますので、改めて一読し、そうした行為に抵触しないようにしましょう。
たとえば、以下のような行為をアカウント規制の対象としています。
- 返信機能を使って、多くのアカウント宛てに重複した返信や一方的な返信を繰り返すこと
- 注目を集めるために、トレンドトピックと無関係のツイートをすること
- 重複したリンクを多数投稿するなど、他のユーザーの検索品質を低下させること
など
X(Twitter)のロゴについて
X(Twitter)のロゴは、ブランドツールキットからダウンロードすることができます。
入手できるロゴはブラックかホワイトの2種類。どちらを使用するかは、背景の色にあわせて選ぶことができます。

ロゴの使用にガイドラインを設けているSNSもありますが、X(Twitter)のロゴの使用には、今のところ具体的な規定がありません。ただし、ロゴのダウンロードページには「ロゴをどのように使⽤するかについては、時間をかけて慎重に検討してください」とあるため、Xのブランドを毀損しない使用方法どうかを一度考えてから、慎重に使用するようにしましょう。
まとめ:ルールを守ってX(Twitter)を活用しよう
X(Twitter)の利用規約は定期的に改定されるため、継続的にチェックする必要があります。そうすることで、知らない間に規約違反を犯してしまった、何らかのリスクにさらされてしまったということがないようにしましょう。
最近では、AI学習へのコンテンツの使用が明記されて話題になりましたが、AI学習にコンテンツを使用されたくない場合は、オプトアウトの設定を行うこともできます。自社の運用に大きく関わる規約が改定されたときは、慌てずに規約をしっかりと読み解き、対応を検討するようにしましょう。
X広告認定代理店でもある株式会社コムニコでは、X(Twitter)の運用に関する相談をお受けしています。課題や予算に応じて、公式のAPIを活用した自社開発のX(Twitter)投稿管理ツール「コムニコ マーケティングスイート」やX(Twitter)キャンペーンツール「ATELU(アテル)」の提供も可能ですので、何かお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
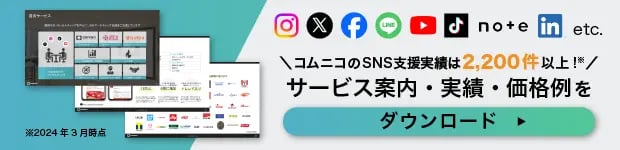 >>株式会社コムニコとは?サービス資料をダウンロード
>>株式会社コムニコとは?サービス資料をダウンロード
>>コムニコにX(Twitter)運用を相談する
-1.jpg?width=90&height=90&name=S__14540804%20(1)-1.jpg)
フリーランス編集者として大手出版社の雑誌・書籍を担当後、コムニコへ。SNSコンテンツクリエイターとして、高知県観光のSNS支援では9ヶ月でフォロワーを約15倍に拡大など、さまざまな業種のアカウント支援を担当。「We Love Social」では、編集長として100以上の記事を執筆し、メディアを月間最大37万PVに成長させた。本質的な信頼を育む「ラバブルマーケティング」を実践する、SNSエキスパート協会認定講師(SNSエキスパート検定上級資格保有)。











