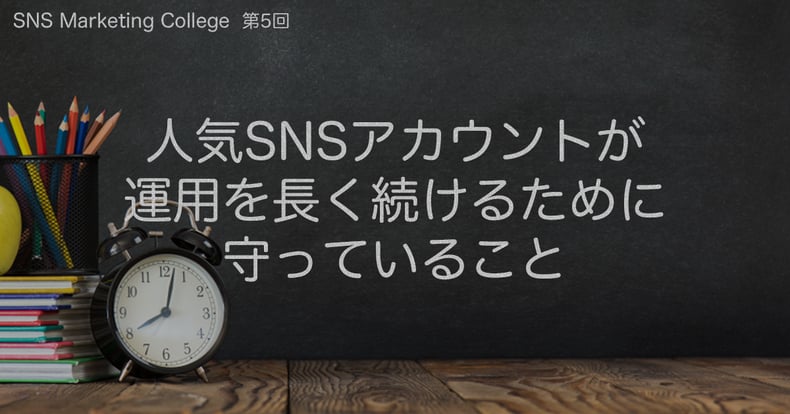
この記事ではSNSアカウントを安定的に運用していくために、運用前に決めておくべきことを紹介します。
■目次
意識や姿勢づくりの基礎となる「運用ポリシー」
SNS運用を続けていると、様々な予期せぬ事態が生じることがあります。万が一、そのようなことが起こってしまった場合でも慌てずに対応するために、「運用ポリシー」の整備をしておきましょう。
行動指針となる「運用ポリシー」を定めよう
「運用ポリシー」とは、閲覧者向けにSNSで発信していく目的や、コンテンツの方向性などの行動指針を定めたものです。自社のSNSアカウントを運用するうえで、担当者が複数名いる場合にどうしても起こってくるのが「意識や考え方の違いによる方向性の迷走」です。これは、担当者が自分だけ、という場合でも、その時々で方向性が変わってしまうこともありますし、突然の異動による担当変更などで常に起こりうる問題です。
「運用ポリシー」を決めておくと、複数名でアカウントを運用する場合でも、どのようにそのSNSを活用し、盛り上げていくか「目標」や「目的意識」を共有することができます。この「目的意識」の共有が無い場合、キャンペーンやコンテンツが計画倒れしてしまったり、細かな部分でのミスコミュニケーションが頻発したり、という事象が発生します。
「運用ポリシー」は「ルール」ではない
「何か決まり事を作る=ルール」と考えてしまいがちですが、「運用ポリシー」は「こんな姿勢でユーザーと交流していこう!」という緩やかな方針であり、「ルール」や「ノルマ」とは異なります。
「ルール」や「ノルマ」としてきっちりと枠を決め、強制してしまった場合、メンバーの自由な発想を妨げてしまうことになりかねません。
コカ・コーラシステム(日本コカ・コーラ株式会社や製品の製造・販売を行うボトラー社、関連会社など)やシャープ株式会社などは、ガイドラインやポリシーを定めたうえで外部に公開しています。

参考:コカ・コーラシステム ソーシャルメディアの利用に関する行動指針

参考:シャープ公式Twitterアカウント コミュニティ・ガイドライン
個人情報の保護など絶対に押さえておかなければいけない部分はルールとして定めていますが、基本的には考え方や方向性などについての緩やかな指針となっています。
「運用ポリシー」は、閲覧してくれるユーザーや自社のファンとよりよいコミュニケーションをとるために「どのような姿勢で対応するか」という目安のようなものだと思ってください。
安定運用のための「運用マニュアル」
「運用ポリシー」のほかに用意しておきたいものとして「運用マニュアル」があります。「運用マニュアル」は内部ルールのようなもので、「運用ポリシー」で方向性を決め、「運用マニュアル」に沿って実際に安定した運用を行なっていきます。
具体的には、投稿時間や頻度、原稿やクリエイティブ作成時のフロー、投稿の形式などを明確にしておくと良いでしょう。
決めておく事項の例
- 投稿の頻度(1日1回、週に2〜3回 など)
- 投稿する時間帯(9:00~17:00の営業時間内に投稿 など)
- 写真や動画のルール(形式、選定基準など)
- トンマナやレギュレーション(口調や語尾、中の人やキャラクター、絵文字や顔文字の有無 など)
- 投稿フロー(投稿時のチェックや、誤投稿時の対応、コメント対応について など)
例えば、投稿の頻度に関して何も決めていないと、告知したいことが複数ある日は何回も投稿する一方で、別業務が重なり何日も投稿が途絶えてしまうということになりかねません。
投稿についての決まり事を「運用マニュアル」として定めておくことで、ナレッジをためやすくなり、チームでの共有、対応が容易になります。
担当者の異動、退職などによる引継ぎを容易にし、アカウント閉鎖のリスク回避のためにも役立ちます。
また、「運用マニュアル」作成時に含めておきたいのが定例ミーティングについてです。週次や月次で定例ミーティングを行い、次の投稿に反映していくためのフロー図があると便利です。作成の際には、下記の例のようにミーティングの頻度やどの部署と何の話し合いをするか、ということを明確にしておくと良いでしょう。

万一のための「体制づくり」
複数名で運用する場合、業務分担が必要となります。そこで、おすすめしたいのが体制図の作成です。人数が増れは増えるほど、1人ずつの負担は軽くなりますが、誰が責任者なのか曖昧になります。役割を明確化させ、管理表や組織図といった形に作成しておくとよいでしょう。
- 責任者(リーダー):運用ルールやクオリティの最終確認 など
- 主担当:プランニング、効果測定、コメント返信 など
- サブ担当:コンテンツづくり(ライティング、画像作成) など
突然の仕様変更やプラットフォーム側の不具合などに、管理・運用の体系化やマニュアルを整備しているかどうかで対応スピードに大きな差が出ます。対処法や報告・対応ルートを明確化しておくと同時に、こまめなアップデートを欠かさないようにしましょう。
また、複数部署による投稿のチェックや承認作業が必要になった場合、各部署ごとに時間や内容を調整・管理し、連携をはかるのは非常に手間がかかることです。このような場合は、SNSの管理ツールの導入を検討するのもよいでしょう。ツール上で予約した投稿が未承認のまま投稿予約時間に近づいた際にアラートが届くなど、便利な機能もあります。
まとめ
企業としてSNSアカウントを運用していく場合、当たり前ですが個人で好きな投稿をするのとは全く異なります。人気のアカウントに育てていくためには、チームで知恵を出し合っての運用となっていくことでしょう。
一定のクオリティを担保した上で安定した運用を複数名で管理・運用するためには目安を作る必要があります。「運用ポリシー」や「運用マニュアル」、「体制図」の作成は、そのための手段のひとつです。
人気アカウントを作り出し、安定して運用するために基礎となる部分からしっかりと固めていきましょう。
マニュアルやポリシーの策定は、コムニコで支援を行なっています。作成に困ったら、お気軽にご相談ください。
参考文献:林 雅之『デジタル時代の基礎知識『SNSマーケティング』 「つながり」と「共感」で利益を生み出す新しいルール(MarkeZine BOOKS) 』(株式会社翔泳社・2018年・P52〜55)

マーケティングプランナーとして、「We Love Social」の編集やメールマーケティングを担当しています。 猫が好きで、プライベートでは猫の保護活動をしています。












